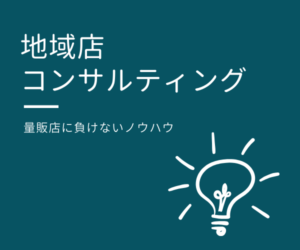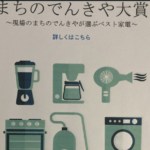新型コロナウィルスに関する政府の説明で、自民党の河野太郎防衛相は「カタカナ語が多すぎて、よく分からない」と述べたという。「日本語で言えば良いのではないか」と指摘したようだ。
「ライブハウスでクラスターが起き、それがオーバーシュート、パンデミックに繋がっていく。東京をロックダウンせざるを得なくなる」――。確かにこれでは、話しが分からない。
「ライブ会場で集団感染が起き、それが感染爆発、世界的流行に繋がっていく。東京を封鎖せざるを得なくなる」と伝えた方が理解しやすいし、何よりも緊張感が伝わる。
なんとなく分かったつもり

企業の会議や資料でも、アジェンダ(計画、予定表)、エビデンス(証明、言質)、オーソライズ(公認、正当)、クロージング(クライアントに購入や契約を決断させること)、コミット(責任を伴う約束、決意表明)などカタカナ語が多用されている。
カタカナ語といえば、技術的な専門用語が頻繁に使われているのが、AV機器や通信機器、カメラメーカーが制作する取扱説明書、いわゆる「トリセツ」である。
カメラの場合、スローシンクロ(手前と背景の両方の被写体を明るく撮影する方法)、ハイキー(露出オーバー気味)、ローキー(露出アンダー気味)などといった技術用語が満載で、初心者の敷居を高くしている。
カメラ系量販店ではさすがに分かりやすい言葉で説明してくれるのだが、家電量販店では戸惑う。こちらが初心者なのを知っているのに、専門用語を羅列する。欲しい気持ちもトーンダウンする。
これではメーカーの技術者が作るトリセツと全く変わりない。本当は理解していないのに、なんとなく分かったつもりでカタカナ語や専門用語を平気で使っている。
そうした意味では政府の役人もメーカーの技術者も、家電量販店の売り場担当者も同じ。つまり、顧客視点に欠けているということだ。